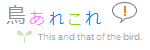鳥メモ
鳥に関して興味の沸いた雑学的なことを随時書いてるページです。
- 世界の野鳥の種数はおよそ9000種。ただ、研究者によってある程度ばらつきがある。2011年のIUCN(国際自然保護連合)の鳥類の既知種数は10027となっている。(「IUCNレッドリスト2011掲載種数」)
- 鳥類最大の目はスズメ目。全体が9000種で、スズメ目は5000種をしめる。
- 鳥類最大の科はヒタキ科。1400種類ほどになる。
- 世界の鳥の90%は陸鳥。それに対し、日本では南北に長いため、北方系や南方系など多様に富んでいるため、水鳥のほうが若干多い。
- 鳥類全体の内、海鳥は3%
- 世界の野鳥の種数は亜種も含めるとおよそ25000種。種と同様に、これもばらつきがある。(「鳥の世界」(1969)ほか)
- これまで地球上に現れた鳥の種数は16万種。これは始祖鳥誕生以後に現れた鳥の種数。(「世界鳥類事典」)
- 日本の固有の野鳥は約15種類(ヤマドリ、ヤンバルクイナ、アマミヤマシギ、アカヒゲ、リュウキュウカラスバト(絶滅)、オガサワラカラスバト(絶滅)、アオゲラ、オガザサワラガビチョウ(絶滅)、アカコッコ、オオトラツグミ、メグロ、オガサワラマシコ(絶滅)、ルリカケス、ミヤコショウビン(絶滅)。
- 世界一大きな鳥はダチョウ。雄では体長が2.5mに達する。また、世界一重い(100kgを超える。大きな個体では150kgあるとか)鳥でもあり、眼球は陸生動物では最大の5cmほどの大きさ。
- 世界一小さい鳥はマメハチドリ。体長は6cm程度。また世界一軽く2g程度。(「野鳥と自然の解説実践ハンドブック」(2002)他)
- 渡りの距離が世界一長い鳥はキョクアジサシ。片道1万8000km。往復では3万6000kmほどにもなる。
- 翼開長が一番大きい鳥はワタリアホウドリ。翼開長は3.5mにもなる。翼開長とは、翼を開いたときの翼の端から端までの長さのこと。
- 世界一早い速度で飛ぶ鳥はハヤブサ。急降下しているときの速度は時速130kmや180kmまたはそれ以上の計測値が出されています。(「世界鳥類事典」(1996)他)
- 世界一飛ぶのが遅い鳥はアメリカヤマシギ。ディスプレイフライト(求愛や誇示行動の意味を持つ飛行)をしているときでは、時速8km。
- 世界一嘴の長い鳥はコシグロペリカン。嘴の長さは50cm。モモイロペリカンもほぼ同じ長さ。(「鳥の雑学がよ〜くわかる本」)
- 体長と比較して最も嘴の長い鳥はヤリハシハチドリ。体長の25cmの内、嘴の長さは10cm。
- 最も嘴の短い鳥はシロハラアマツバメ。
- 世界一泳ぐのが速い鳥はジェンツーペンギン。瞬間的な速度では時速30kmに達するという。
- 世界一高い所を飛んだ鳥はマダラハゲワシ。1万1274m(11278m?)の高さを飛んでいるのが確認された。1973年、コートジボワールの沖で飛行機に衝突したという。
- 最も深く潜る鳥はエンペラーペンギン。エンペラーペンギンは水深630mまでもぐった記録があるという。潜水時間が最も長い鳥もこの鳥で20分間ももぐっていられる。
- 野鳥のうち、世界一尾が長い鳥はカンムリセイラン。尾の長さは1.7m。野鳥でなければ、オナガドリが一番長い。
- 体長に比較して、世界一脚の長い鳥はセイタカシギ。脚の長さが体長の約60%に相当する。
- 飛べない鳥のうち世界一小さいのはマメクロクイナ。その大きさは12.5cm。
- 飛べる鳥のうち、世界一深く潜れる鳥はハシグロアビ。81mほど潜る。
- 飛べる鳥のうち、走るのが最も速いのはオオミチバシリ。20〜35kmほどの速度で走れる。また、世界一高く跳躍でき、3mもの高さになるという。(「世界鳥類大図鑑」(2009)他 )
- 飛べる鳥のうち最も重いのはアフリカオオノガンで、重い固体は22kgになるという。
- 世界一小さい猛禽類はボルネオヒメハヤブサ。その大きさは15cm前後。スズメほどの大きさ。また、「アジアモモグロヒメハヤブサ」もほぼ同じ大きさ。
- 世界一小さい海鳥はコウミスズメ。その大きさは14cm。
- 世界一脚が短い鳥はアマツバメ(類)。はかっているのはふ蹠と言われる踵から足指の上部までの長さ。その長さは1cm前後。
- 最長寿の記録を持つ鳥はエジプトハゲワシ。シエンブルーン動物園で飼育されていた個体で、118年生きたということです。(「鳥のおもしろ行動学」)
- 現在、世界一数の多野鳥はコウヨウチョウ。その推定値は15億羽。この鳥は、100万羽以上の群れをつくり、農作物に多大な被害を与えるので、毎年2億羽も駆除されているが、総数には影響がないとのこと。また、大量に狩られたことで絶滅したリョコウバトは、最盛期の総数は50億羽といわれていた。
- 世界で最も南に生息する鳴禽類はサウスジョージアタヒバリ。(「世界鳥類大図鑑」(2009))
- 一腹卵数が世界一多い鳥はヨーロッパヤマウズラ。平均18.3個。最高では28個も産むという。
- これまでで最大の翼開長を持つ鳥はアルゲンタピス・マグニフィケンス。その翼開長は8mであった。(7mかそれ以上という説も)(「世界鳥類大図鑑」(2009),「動物大百科 7 鳥類1」(1986))
- 鶏の生産羽数が最も多いのは中国で、その数は43億羽。世界の生産羽数の4分の1を占めている。(「鳥学大全」(2008))
- オニオオハシの大きなは15gもない。オニオオハシの嘴は長さがおよそ20cmもある。
- 鳥類のほとんどは1kg以下、50cm以下。(「鳥の起源と進化」(2004))
- 鳥類は歯がないが、この代わりになるのが砂嚢(さのう)である。小石や砂を蓄えておき、食物をすりつぶす。
- 鳥類の翼は親指、人差し指、中指の3本の指からなる。(「鳥の起源と進化」(2004),「鳥の骨探」(2009))
- 鳥類の平熱は41度程度。夜には体温の低下も見られる。(「野鳥の医学」)(1997)
- 鳥の多くは尾脂腺を持っている。ここからロウ状の脂を分泌し、羽に塗り水をはじく。これによって体温を保てる。(「鳥の起源と進化」(2004))
- 羽毛が体重に占める割合は、5%〜7%。羽毛の数は体の大きさによって異なる。大きいほうが多い。たとえば、ナキハクチョウで25216本、小さなノドアカハチドリで940本という値がある。タカやワシなどでは15%前後になる。(「鳥類学辞典」(2004),「世界鳥類事典」(1996))
- 鳥の胸筋は体重の15〜25%。ハチドリでは、体重の30%を飛ぶための胸筋が占める種類もいる。人間の胸筋は、体重の1%にも満たない。
- 水面に飛び込んで餌をとる鳥は気嚢(きのう)をうまく利用している。気嚢は水面にぶつかる際の衝撃を和らげることに使っている。ゆえに、ダイビングをする鳥は特に気嚢が発達している。
- 「アンナイドリ」という名前の鳥がいる。採食の際に、コトドリについていくことからこの名がついた。(「世界鳥類大図鑑」(2009))
- 果物のキウイと鳥のキーウィ。名前が先についたのは鳥のキーウィ。キウイフルーツは外見がキーウィに似ていることからこの名になった。キーウィは声が由来。
- もともとペンギンとは、オオウミガラスを指す言葉だった。オオウミガラスの姿に似ていたことから、現在のペンギンが「ペンギン」と呼ばれるようになった。ペンギンの語源はラテン語で脂肪という意味の「Pinguis」に由来するとする説などがある。
- ニワトリの原種はセキショクヤケイ。これは、チャールズ・ダーウィンのセキショクヤケイ単一起源説によるもの。これを支持する研究者は多い。 ヤケイには他に3種類いて、「ハイイロヤケイ」、「セイロンヤケイ」、「ミドリエリヤケイ」があり、これらが祖先とする多元説もある。(「鳥学大全」(2008)、「鶏の事典」(1968)、「カラー版 日本鶏・外国鶏」(2004))
- 鳥の化石はおよそ800種類見つかっている.鳥の骨はできるだけ軽くするために中が空洞になっている。そのため、化石として残ることが少ない。
- 鳥類の91%が一夫一妻で繁殖する。一夫一妻を「一繁殖期間、特定の雄と雌が結びついている」とした場合。(「新版 動物の社会―社会生物学・行動生態学入門」(2006))
- ダチョウは雛を翼で覆って、雨や日差しから守る。(「世界鳥類大図鑑」(2009))
- ワシやタカの仲間の視力は人間の8倍。人の目と違い、ワシやタカの目には毛細血管が無い、視細胞が人の5倍もある、などの理由からこのような視力になる。
- キツツキフィンチはサボテンの棘を使って木の皮の割れ目から虫を引きずり出す。(「世界鳥類大図鑑」(2009))
- 抱卵しない野鳥はツカツクリ類だけ。ツカツクリは、その名の通り、落ち葉などで塚を作り、その中で卵を温める。(「世界鳥類大図鑑」(2009))
- ハチドリの仲間はホバリング中に秒間55回ほど羽ばたく。これは平均的な値で、大型種では10回前後、小型種だと80回前後羽ばたく。
- 赤道直下に生息するペンギンがいる。そのペンギンは、ガラパゴス諸島のガラパゴスペンギン。近くにある、フンボルト海流の冷たい水のおかげで生きていられる。
- ペンギンは南半球にしか生息していない。ガラパゴス諸島に生息するガラパゴスペンギンは例外的に、一部北半球で生息しているといえるかもしれない。
- 托卵で有名なカッコウの仲間で托卵をするのは135種類中53種類。カッコウの仲間は世界に135種類いる。日本にはカッコウ、ツツドリ、ジュウイチ、ホトトギスの4種類がいてどれも托卵する。(「鳥類学」)
- 走鳥類が南半球に多い理由は2億年前にさかのぼる。2億年前の地球は北にローレシア大陸、南にゴンドワナ大陸があり、走鳥類の祖先はゴンドワナ大陸にいた。その後、大陸が今の位置になり、南の大陸にいた走鳥類は南に多くなった。しかし、これに対し、DNAの分析によると最近に分岐したとも言われている。
(「生態学 個体・個体群・群集の科学」(2003),「世界鳥類大図鑑」(2009))
- 砂漠に生息するサケイ類は羽毛で水を運ぶ。特殊な羽毛に水を吸収し、雛に飲ませる。(「鳥類学」(2009))
- 真正托卵する鳥はおよそ90種。全体の1%ほどだが、例外的な存在としては多いほうである。このうち、50種ほどはカッコウ科の鳥。ほかには、ハタオリドリ科、ムクドリモドキ科、ミツオシエ科、カモ科の4目5科が托卵をする。種内托卵は少なくとも16目234種で確認されている。(「鳥たちの生態学」(1986)「鳥類学」(2009))
- 夜行性の鳥は全体の3%。フクロウ類、ゴイサギ、ヤマシギ、ヨタカなどが有名。
- ペンギンなどの雛は体に脂肪を蓄えている時期に親よりも大きくなる。
- 托卵鳥の雛は生まれてすぐに巣にある卵を落とす。目すら見えない状態で、孵化して触れたものを巣から落とす。アフリカの托卵鳥、ミツオシエの場合は少し違っていて、その雛は、宿主の雛をかみ殺す。そうできるのも、雛には、嘴に鉤がついているから。殺した後には抜け落ちる。
- タンチョウの頭の赤い部分は羽毛が生えていない。赤く見えるのは血液が透けて見えるため。
- 尾羽のない鳥はいない。カイツブリなどは尾羽が無いようにも見えるが、実際にはちゃんとある。
- 最も鼻の利く鳥はキーウィ.鳥類は一般的に嗅覚が乏しいがキーウィは例外。また、キーウィは視力が弱く、飛べない鳥である。(「鳥の世界」(1969))
- ワニの口の中に入る鳥がいる。川岸に休んでいるワニの口の中に入り、その歯の間に残った餌やヒルなどを食べる。
- ツメバケイの雛は危険が迫ると水中に飛び込む。水中に逃げ込んだ後、岸辺まで泳ぐ。そして、ツメバケイの雛にある爪を使って木を登っていく。
- 木の枝に擬態する鳥がいる。それは、アフリカオオコノハズク。天敵を見つけると、体を非常に細くして、木の枝のようになる。また、ハイイロハチヨタカも同じように木の枝のように見せる。
- 脊椎動物に含まれる綱で胎生の種がいないのは鳥綱だけ(鳥類は卵生の種しかいない)。(「鳥の進化と起源」(2004))
- 飛びながら眠る事ができる鳥がいる。アマツバメ類は飛翔能力に長けていて、片脳ずつわずかな間だけ眠らせて、飛びながら寝ることができる。
- ヤドリギしか食べない鳥がいる。それはヤドリギハナドリ。(「生態学 個体・個体群・群集の科学」(2003))
- 毒をもつ鳥がいる。ズグロモリモズ、カワリモリモズ、サビイロモリモズなど。この順に強い毒性を持つ。毒性が高い部分は、皮膚、羽毛、筋肉の順。この毒はステロイド系の神経毒で神経を麻痺させる作用がある。この三種が毒をもつ理由は寄生虫からの防御のためと考えられている。毒を投与した個体のうち50%が致死するという値 LD50値(半数致死量)は 0.002mg/kg。(「猛毒動物 最恐50」(2008))
- 冬眠する鳥がいる。その鳥はプアーウィルヨタカ。鳥類では唯一冬眠する鳥だといわれる。岩の割れ目の中で、体温を18度ほどに低めて長いときでは、88日間同じ状態でいることが確認された。目に光を当てても反応は無く、鼻孔に鏡を当てても曇りも無く、聴診器を使っても心音さえ聞こえない状態になっていたが、それでも春には、飛び立つという。
- カラスが「からす」と呼ばれ始めたのは奈良時代。江戸時代中期から種類を区別して「はしぶと」、「はしぼそ」といわれた。(「図説 鳥名の由来辞典」(2005))
- スズメも奈良時代から「すずめ」、「すずみ」という名で呼ばれた。しかし、万葉集にはこの鳥を詠んだ歌が一首もない。(「図説 鳥名の由来辞典」(2005))
- 鳥で最も軽い脳がハチドリで0.17g、最も重いものでダチョウの42g。BB弾が約0.2gくらい、鶏卵のSSサイズがおよそダチョウの脳ほどの重さ。「鳥脳力」(2010))
- 羽ばたきの推力を考えると始祖鳥は飛び上がることができたかもしれない。または羽ばたきは木に登る手助けになっていた。(「鳥脳力」(2010))
- 同種に愛着があるのは生得的なもの(同種を見ることで発現)。(「鳥脳力」(2010))
- 必要に応じて脳が大きくなるのは、カナリアの高次歌中枢の大きさが歌う時期で変わることからわかった。(「鳥脳力」(2010))
- 鳥が道具を利用するのは、石でダチョウの卵を割るハゲタカやサボテンの棘や小枝を使うダーウィンフィンチなど26種類が知られている。(「鳥脳力」(2010))
- ハトを通信手段として用いたのはメソポタミアが発祥の地。(「鳥脳力」(2010))
- 鳥類で抱卵や給餌などを手伝うヘルパーは250種類ほど。(「イラスト図説「あっ!」と驚く動物の子育て」(2006))
- サイチョウはメスが樹洞に閉じこもって抱卵、育雛する。雌に餌を運ぶ雄は疲労で死ぬことがあるが、その場合には独身の雄が代わりに餌を運ぶようになる。(ヘルパーになる)(「イラスト図説「あっ!」と驚く動物の子育て」(2006))
- キジバトはそのうから出すピジョンミルクで子育てする。(「イラスト図説「あっ!」と驚く動物の子育て」(2006))
- ドードー(Dodo)という名前の由来はポルトガル語の「のろま」という意味、あるいは鳴き声由来の説がある。アメリカ英語でもdodoという単語は「まぬけ」といった意味を持つ。同じくアメリカ英語では「絶滅した存在」という意味も持つ。(Wikipedia ドードー)
- アホウドリという名は江戸時代初期には知られていて、当時すでに「信天翁(しんてんおう)」や「沖の大夫(たいふ)」といった呼称もあった。アホウドリの漢字名が「信天翁」と書かれる場合があるが、これは漢名(中国での名前)であり、天信じ天に運を任せる、という意味。「図説 鳥名の由来辞典」(2005)
- エトピリカ、ケイマフリの名前はアイヌ語に由来する。エトピリカは嘴・美しいという意味で、ケイマフリは赤い脚という意味である。ともにチドリ目ウミスズメ科の鳥。英名はエトピリカがTufted Puffinで tuftedはふさ飾りのついたという意味で(tuftはふさ、しげみ)、puffinはツノメドリ属のこと。「房飾りのついたツノメドリ属」という意味。ツノメドリの英名はSpectacled Guillemot。spectacledが眼鏡をかけた、または眼鏡の形の斑紋があるといった意味でケイマフリの目の周りの白い模様をあらわしている(夏羽で目立つ)。guillemotは近縁の種のウミガラスの意味。つまり「眼鏡模様を持つウミガラス」の意味になる。 (「図説 鳥名の由来辞典」(2005)
- ギネス記録となっている最大の鶏卵の重さは176g。Mサイズの鶏卵で60gくらい、ダチョウの卵は1kg以上。(Wikipedia 鶏卵)
- 「bird」の語源は「brid」元々はbridという形だったが、15世紀にはiとrが入れ替わり、現在の形になった。古英語では鳥の意味としてはfogolという単語ほうが一般的で、これはゲルマン語派のfugla(鳥)に由来している。fugla(鳥)はfly、つまり飛ぶといった意味のゲルマン語派のfluglaの変形。(参考。自信がない。)
- 一夫多妻の鳥は全体の2%。これはダチョウなどが含まれる。一妻多夫の鳥は全体の1%。これにはタマシギなどが含まれる。タマシギは雌のほうが鮮やかな姿でオスは地味という性的二型であり、抱卵もオスが主に行っている。「鳥類学」p368(2009)
- ミズナギドリ類は胃に油分を溜め、敵が近づくと威嚇のためその油分を吐きかけることがある。通常はこの油分は雛の餌となっている。「鳥類学」p177(2009)
- ヒゲワシの主食は骨。消化能力に優れていて、牛の脊椎骨さえ二日で消化できるらしい。「鳥類学」p177(2009)
- 鳥の腸管の長さは平均で体長の8.6倍。ただし、種類によって体長との比率は大きく異なる。長いものではダチョウの20倍、短いものではヨーロッパアマツバメの3倍。因みに、人間の腸は体長の4倍から5倍。鳥の場合では、果実、肉、虫を食べる種類で腸が長く、種子、魚を食べるもので短い傾向があり、先のダチョウとアメツバメもこの傾向に漏れず、ダチョウは主に植物を、アメツバメは虫を食べている。ただ、この二種類は体長もかけ離れているし、走鳥類であるダチョウに対し、アマツバメはかなり飛ぶことに進化しているという違いもあり、腸の長さの比率は食性だけによるとは言えないだろう。「鳥類学」p177(2009)
- 夜に寝る場所であるねぐらは、種によって異なる営巣場所と同じような場所である傾向がある。樹上に営巣するものは樹上をねぐらとする、という感じである。海上で眠るもの、岩棚で眠るもの、地上で眠るもの、水辺の茂みで眠るもの、あるいは空中で眠るものなど様々である。または、巣をねぐらとして活用する鳥もいる。「鳥はどこで眠るのか」
- ライチョウの仲間は、雪の中で寝ることがある。特にカラフトライチョウは雪を掘り、かまくらのような形を作りその中で寝ることがある。他にもスズメ目の小鳥の中でも断熱されて外気より暖かい雪の中で寝ることがある。「鳥はどこで眠るのか」p30-
- 鶏卵に黄身が二つ入っていることがあるが、これが仮に孵化するものだとしても双子の鶏が生まれるわけではない。別々に発生を始めるがたいていは一方だけが育ち、生まれるときには一個体だけが出てくる。(動物たちの奇行には理由がある)
- 鳥が威嚇や攻撃するときに、嘴を開いて噛みつくようにするが、爬虫類であった時の名残。爬虫類には歯があるが、鳥類には歯がない。(動物たちの奇行には理由がある)
- 地球温暖化によって種の小型化が起こっている可能性がある。まず、寒いほどに体が大きい傾向がある、という内容のベルクマンの法則(規則)というものがあり鳥類はこの法則に当てはまっている。一部の種においてここ100年の気温の上昇によって体の小型化が進んでいる可能性があるという。(Gardner et al.2009)「カラスの自然史」
ページの作成:09/04/19 最終更新(補足追加等含む):12/05/26